2023.03.15
スタッフブログ
南を向かない家
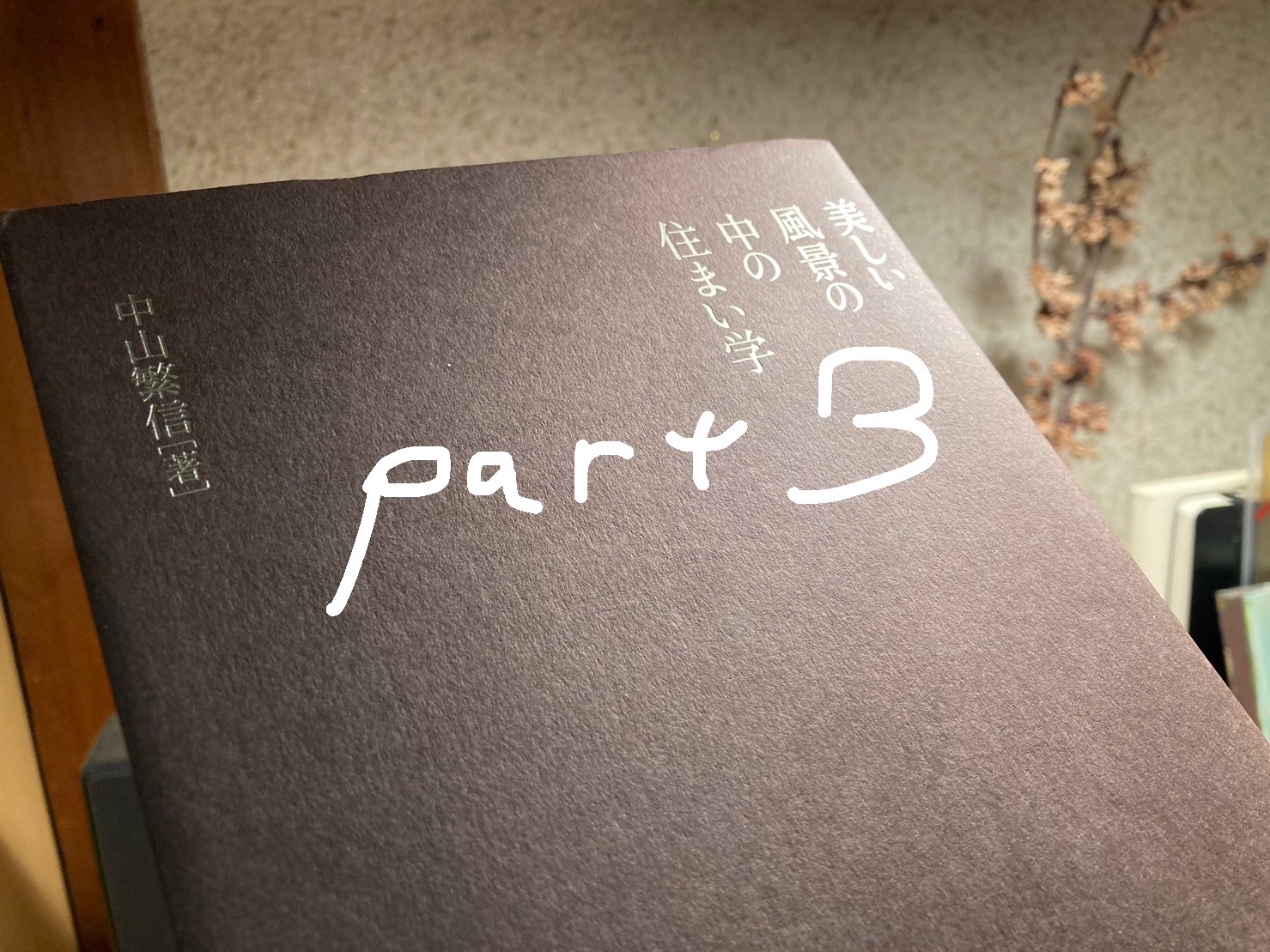
輪和建設、大工の國分です。
美しい風景の中の住まい学を読んでます。
その中で日本の住宅の形式として大まかに2タイプ、農家と町家について書かれていました。
農家は文字通り農村に立つ家で、広々とした土地を活用して、基本的に家は南を向いています。
彩光の面から考えて住宅は南向きの方が良いというのは共通認識で、マンションとかでも南向きの部屋は北向きの部屋より値段が良かったりしますね。
しかも太陽の光には殺菌効果もあるため、なおさらです。
しかし、日本には南を向かない住宅があるようです。
それが町屋。
京都や奈良を筆頭に昔に町として栄えた場所に建っている、あの細長い建物たちです。
町屋が向くのは南ではなく、道でした。
お客様は道から来るから、道に向けて開けた作りになっているのですね。
また人々が密集して暮らし、土地も広く取れず(当時は間口の幅で税金が決まっていました)、農家のように自由に彩光面を確保するのは不可能だったでしよう。
しかし、そんな町屋ですが、快適な住環境を手放したわけではありません。
縦長の建物には道から家の裏まで抜ける土間(通り庭)があり、家の中央部には坪庭と呼ばれる小さな庭がありました。
坪庭の木々や塀は太陽光を受け、その光を乱反射させることで、家の中に光を届けます。
農村のように直射日光を得ることはできなくとも、このように反射を上手く利用して光を得ているのですね。すごい!
さらに通り庭は煙突効果をもたらし、道に水を撒くことで、その少しの温度差で家の中を空気が通り抜けます。これもすごい!
何だかとても風情がありますね。
この本の著者は、今の日本の住宅は人々が密集して暮らしている環境においても、南からの彩光を確保しようとし、道にそっぽ向いているところに疑問を持っているようでした。
私個人としては、お客様が来る訳ではないですし、これからの省エネじだいに向けて考えると、南からの彩光は重要ですし、道を向く必要もないとは思います。
しかし、道を向いて家が建つ場所の道空間は魅力的ですし、町屋の機能性も参考にしたいところです。
追記:町屋って家と家がくっついているから断熱効果は高そうですね。
「吉野の木を伝統技法で建てる工務店」輪和建設株式会社では、永く健やかな暮らしを求め、自然素材にこだわった奈良の木の家づくりをしています。
奈良・大阪・京都他で注文住宅の新築、リフォーム、古民家再生、古民家リフォームの施工事例はこちら↓


